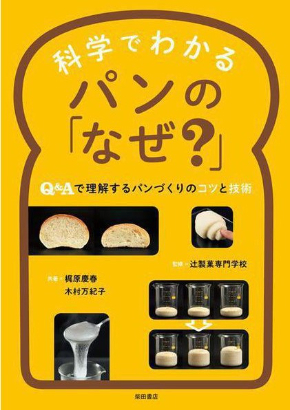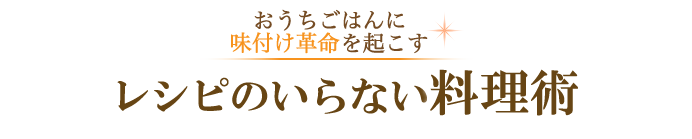【なぜ食パンはちぎれる方向とちぎれない方向がある】
【約100年続く『子供の科学』に掲載されました】
「食パンは、なぜまっすぐにちぎれる方向と、ちぎれない方向があるのですか?」
小6男子の素朴な疑問です。
きっと給食を食べながら、不思議だったのでしょうね。
1924年創刊。
大正時代から続く、
『子供の科学』(誠文堂新光社)
という現在発売中の月刊誌で、お答えしました。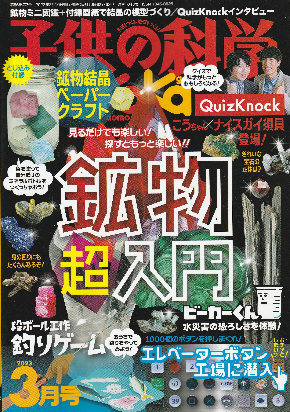
大人は経験的に、
食パンは、
縦にはすっと裂けやすいけれど、
横には裂けないことを、感じて食べてはいると思います。
とはいえ、
なぜ?と子供に急に言われると、
正確な返答は意外と難しくて
「私のほうが、知りたい!」となるかも⁉
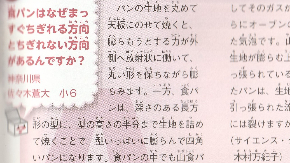
私は、
著書『科学でわかるパンの「なぜ?」』(柴田書店)
監修『パンづくりに困ったら読む本』(池田書店)
の中で、このなぜがわかるように、
パンの作り方の理論については書いてはいますが、
ドンピシャで、このネタはないのです。
そこで、
子供に伝えるときより、深く踏み込んだ内容を
今回はメルマガでお伝えしてみようと思います。
書店では「児童雑誌」のコーナーにあるので、
小中学生のお子さんがいらっしゃる方は、
こちらで説明する大人向けと、
子供にどう話しているかを読み比べてみてくださいね。
***********
食パンって、どんな型で焼くかご存じですか?
山食パンは、
パウンドケーキのような型で。
角食パンは、
それにふたがついた型で。
型の半分の高さまで、生地を詰めます。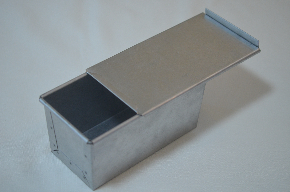
パンは工程中、2度大きく膨らみます。
1度目は「発酵」(30℃)
山食パンの場合は、
一番高い山の部分が、型の上ギリギリのところまで膨らみます。
2度目は「オーブンで焼く」(220℃)
さらに膨らみ、型の上から大きく山が出るくらいに伸びます。
型は底と側面が囲まれていますから、
膨らんだ生地は、上へ上へと伸びていきます。
一方、角食パンではどうでしょうか?
ふたをして焼きますから、
生地が上へ伸びたくても、
ふたにぶつかって頭打ちして、
ふたをした型の中で焼き上がります。
すると・・・
パンのきめに、次のような変化が起こるのです。
同じパン生地を使って焼いた
山食パンと角食パンの写真を見てください。
気泡の形に注目すると
こんな風に違うのです。
●山食パン=縦長の気泡(縦にのびた気泡)
●角食パン=丸く小さい気泡
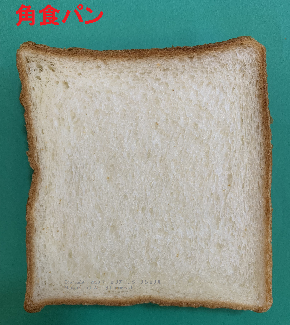
※気泡は、
発酵⇒材料のイースト(パン酵母)が炭酸ガスを出してできたもの
オーブンで焼く⇒発酵でできた気泡や、生地中の水分が、オーブンの熱によって膨張してできたもの
です。
山食パンの気泡は、
生地が上へ上へと膨らんで
縦に引っ張られるために、
縦長になっています。
つまり、生地が上に引っ張られることによって、
流れが縦にできているのです。
だから、山食パンは、縦にしか裂けません。
角食パンは、ふたに生地がぶつかるために
気泡は丸く小さく、詰まった感じになっていますよね。
縦に伸びていることには変わりませんから、
縦に裂けやすいのですが、
山食パンのほうが顕著です。
まぁ、なんて、マニアなんでしょう(笑)
私は食パンを食べるときに、
こんな風に、じーっとサイエンスの目で見ちゃったりしています。
みなさんも明日の朝はパン食ですか?
きっと、縦に裂けるかな、
ってやってしまいますよ(伝染~笑)。
全く同じ生地を使っているのに
見た目でもここまで違います。
そして、食感もまた。
長くなるので、それはまた次回に。
★こういう話が好きな方は、
ぜひ書店で、私の著書をパラパラと読んでみてくださいね。
パンのサイエンスの世界に
引きずりこみます(^^)よぉ~